声の回し方
義江氏の教え
今日は、声を回すことについて書きます。
TV放送が始まったばかりのころのエピソードです。師匠の恩師であった藤原義江丈が、田中角栄総理に「声というのは回すんですよ!」と番組中にレクチャーしたことがあったらしいです。⇒発声法の背景
「声を出すと、息は鼻腔の高い所から低い所におちるため、
次の声を出す前に、
もう一度鼻腔の高いところに戻らなければならないこと」を、
理解していただけると思います。
そのとき「声を口蓋の下に落とさないうちに戻し、声を回して話す方法」があり、
それができるようになると、「声を止めないで息を補給しながら話すこと」ができます。⇒ミッション
それは、息切れしない話し方であり、話しやすく聞き取りやすい話法でもあります。⇒(1)声の出し方
(2)鼻腔・副鼻腔に息をはらんで力を抜くことでは、
眉毛を上げ目を大きくし、頭蓋骨の頭頂部を後ろにずらしながら、
鼻腔・副鼻腔に、息を蓄える「息継ぎ」を紹介しました。
それは同時に、「声を回して」話す事と同じになります。
徳川夢声の語り口
有料レッスンでは、無声映画時代の弁士のまねを取り入れます。
「宮本武蔵」が有名な、徳川夢声氏の語り口を聞いて、
伝説の間の取り方、息の止め方、溜め方について、話し合います。
空気の響く声でうなるように話され、他人には弾んでいるように聞こえてきます。⇒(5)声を出す場所のイメージ
早口で話せる
また、早口を聞き取るには、早口で話せなければできないという法則があります。
声を回す法は、まさに早口で分かりやすく話すための技術になります。
さらに、この「声の回し方」のメリットは、
「思いついた考えが消えてしまわないうちに、話せること」でもあります。
人は、考えが一度にたくさん浮かんでパニックになることがあると思います。
ことばにできるのはそのうちのほんのごく一部ですものね。
早口で解りやすく話せたら、パニックが減るかもしれません。
声を回し、息は常に満タンにしておく
声を回し、大きな呼吸の息継ぎをしないで息の供給ができれば、
思考がストップしないし、
比較的たくさんのことを忘れないうちに早く話すことができそうです。
もっともその前に、変人扱いされてしまうかもしれませんが。
知的な興奮状態のことを思い出していただければ、想像に難くないと思われます。
そういうわけで、頭の回転に声が追いついていけるようになれば、
そんなことは絶対に無理ですが、
それを追求してゆくのであれば、
声としては、だれでも完璧になっていると思います。⇒のどが疲れない音読法
声の回し方は成功してます。
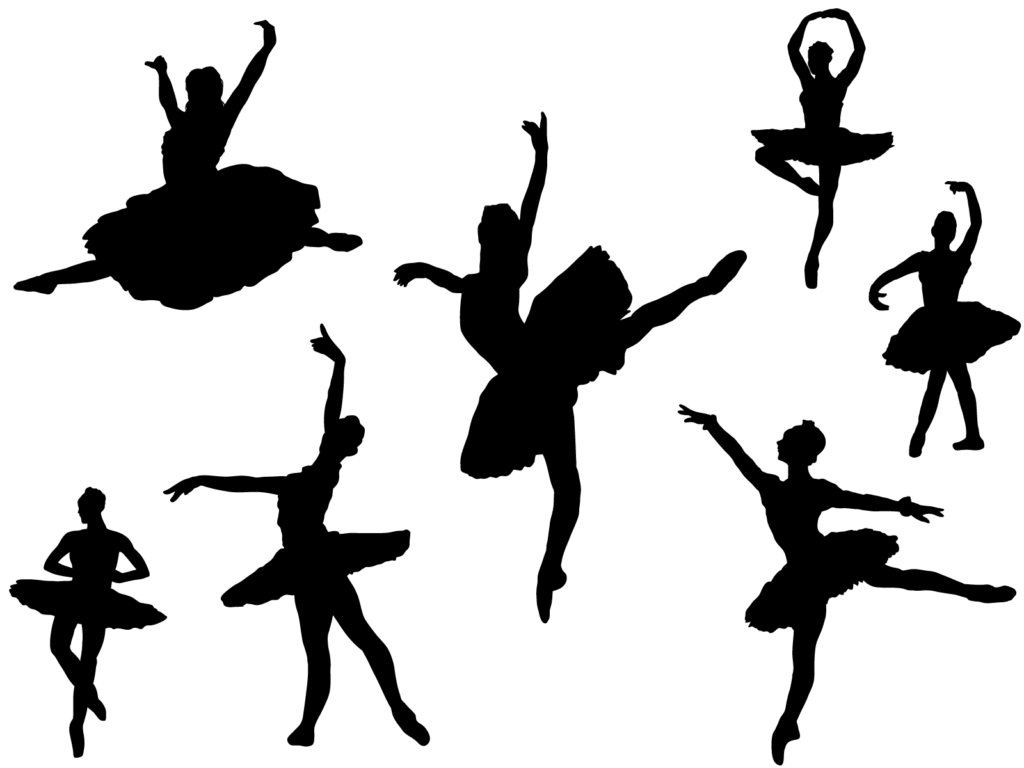
ただし、ここで注意が必要なのは、
それが、暴走するような種類の回転ではないということです。
速さも強弱も再生も停止も、自由自在でなければいけない、
声の回し方のイメージとなります。
眉間のあたり、息の湖面(声を出す場所のイメージ)の上で、
バレリーナたちが、入れ替わり立ち代わり、ステップをしているさまを、
思い描いてみてください。
きっと、緩急あり、強弱あり、リズミカルな、弾んだ素敵な声になるでしょう。
声をのばすときの注意
次に、声を長くのばすときの注意があります。
おしゃべりの声は、それほど息の分量を必要としませんが、
声をのばす、民謡のような歌を歌ったりするときは、
息をわざと持続させるテクニックが必要になってきます。
では具体的に見てみましょう。
スローモーションでしていただけるとわかるのですが、
声を回すことは、発声し始めた時の場所に返るという意味です。
「Oh」というのは、発声法では「オウ」ではなく「オオ」となります。
「オーーー」というのは、「オオオオ」になります。
息は鼻腔・副鼻腔の場所から、離れることはありません。
例えば、「あぁ、そうだねえ」は「ああそおおだねええ」になります。
これは、実践してみないとわからないかもしれませんね。
頭のお鉢(頭蓋骨の一番上の部分)に、息が充満する感じです。
沸騰しやすい人、癇癪持ち、興奮しやすい人は、覚えやすいかもしれません。
でも、そうでない人も、発声法で、癇癪持ちの声は出せるのですね。
大きな声の出し方
サイレンのような、大きな声を出すときも、
鼻腔・副鼻腔から、声がはずれないように、
内圧を頭頂からかけながら、鼻腔の内圧を強めに保っていきます。
スピンジェレすると言って声を「押す」わけですが、
これは、ご自分でされるには、注意が必要です。
つまり、トレーナーが必要です。⇒お問い合わせ
しっかり鼻腔・副鼻腔に声がはめられていなければ、
声は必ず口蓋の下に落ちて、のど(声帯や喉頭)を傷めます。⇒FAQ
息を「押す」(スピンジェレ)といっても、頭頂や眉間に力が入る感じで、
口も下あごもどんどん縦にあいてゆきます。
ちょうど管楽器のトロンボーンが管の長さを変えて高音を出す感じに似ています。
息を鼻腔・副鼻腔の高いところまで、息の補給をしているからです。
このとき、ウエストをきつく締めていると、ゴムやフックがはちきれたりします。
大きなあくびをするのと、似ています。
声を出し続けているときは、
鼻腔・副鼻腔の内圧(空気の分量)をへらさないように、
常にお腹の力で加減することになります。
鼻腔・副鼻腔に息(空気)がなくなれば、必ずのど(喉頭)を痛めます。⇒声で変わる健康
どうしても大きい声を出してみたい方は、こちらに来られてください。
間違った声を出していても、悪い癖が上塗りされるだけで、永久に練習にはなりません。
オペラの声について
さて、大きい声が、イコール、オペラの声と、勘違いされておられる方が昨今多いので、
念のため、ここで確認したいと思います。
正しいオペラの声というのは、
(イタリア語ではオペラの事はメロドラマといいオペラは歌劇だけを指すのではありません)
鼻腔・副鼻腔を響かせて、舞台の中心から、4階の桟敷席まで通る声のことを指します。
強弱がつけられる、セリフがよくわかる声のことをいいます。
みなさまもふだん、無意識に、相手に何かを伝えようとして、
オペラの声を出しておられるかもしれないわけです。
しかし、大きな声で歌を歌おうとすると、
声の回し方が身についていなければ、
どなったり、叫んだり、のどが疲れる歌い方になってしまわれるようです。⇒声の問題~よくある症例
それで、無意識に出しているいい声を、意識してだせるようにするために、
声を回すという発声法があるわけです。
人が無意識に夢中にいい気になって話している時は、
声はおそらく回っているに違いないからです。
⇒参考までに、無言で通じる、或いは声帯を使わず話すこと、
いじめに負けない鼻腔の内圧の力もご覧ください。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
声を回さないと話せない言葉がある
次に、河竹黙阿弥作の弁天小僧次郎吉のセリフで、言ってみましょう。
「知らざあ言って、聞かせやしょう」
これは、声を回さないといえないセリフと思われます。
うまくできなければ、一つ一つ切って、言ってみてください。
「しらあーざあーいっーってえー、きかあーせやあーしょお」
という感じで、-のところを、回しています。ーの所は、余韻です。ただよう息のみです。
できれば、回すだけでなく、どんどん高いところに上がってゆくように
息を補給されると、
すごく格好よくうまくゆきそうな気がします。
黙阿弥のセリフは、五七五になっているので、
音楽的でしゃべりやすいし、きこえやすいし、
記憶にも残りやすいと、いえるのではないでしょうか。
また、あとで触れると思いますが、のどが楽な声、伝わりやすい声を出すには、
黙阿弥のような、リズミカルな話し方も、考えるべきであると、お伝えしておきますね。
コロラトゥーラソプラノ
最後にもうひとつ、声の回し方。
声を回す、というと、
真っ先にコロラトゥーラのことを思い浮かべる方もおられると思います。
もちろん、コロラトゥーラの曲は、声を回して歌わないと、歌えない曲でもあります。

コロコロ転がる鈴の音のように、覚えられてしまうようですが、
コローレというのが、色という意味なので、
カラフルな声ということになるかと思われます。
「ランメルモーレのルチア」の結婚式の「ルチア狂乱の場」のアリアは、
カラフルでコロコロ転がっている美声をきくことができます。
いい曲、名人の演奏は、聞く人の呼吸を穏やかにし、心を癒してくれます。
もちろん、聞いていてこちらの呼吸が楽になってくるのであれば、
その人の声は、最高にいい声だ、ということになるでしょう。

