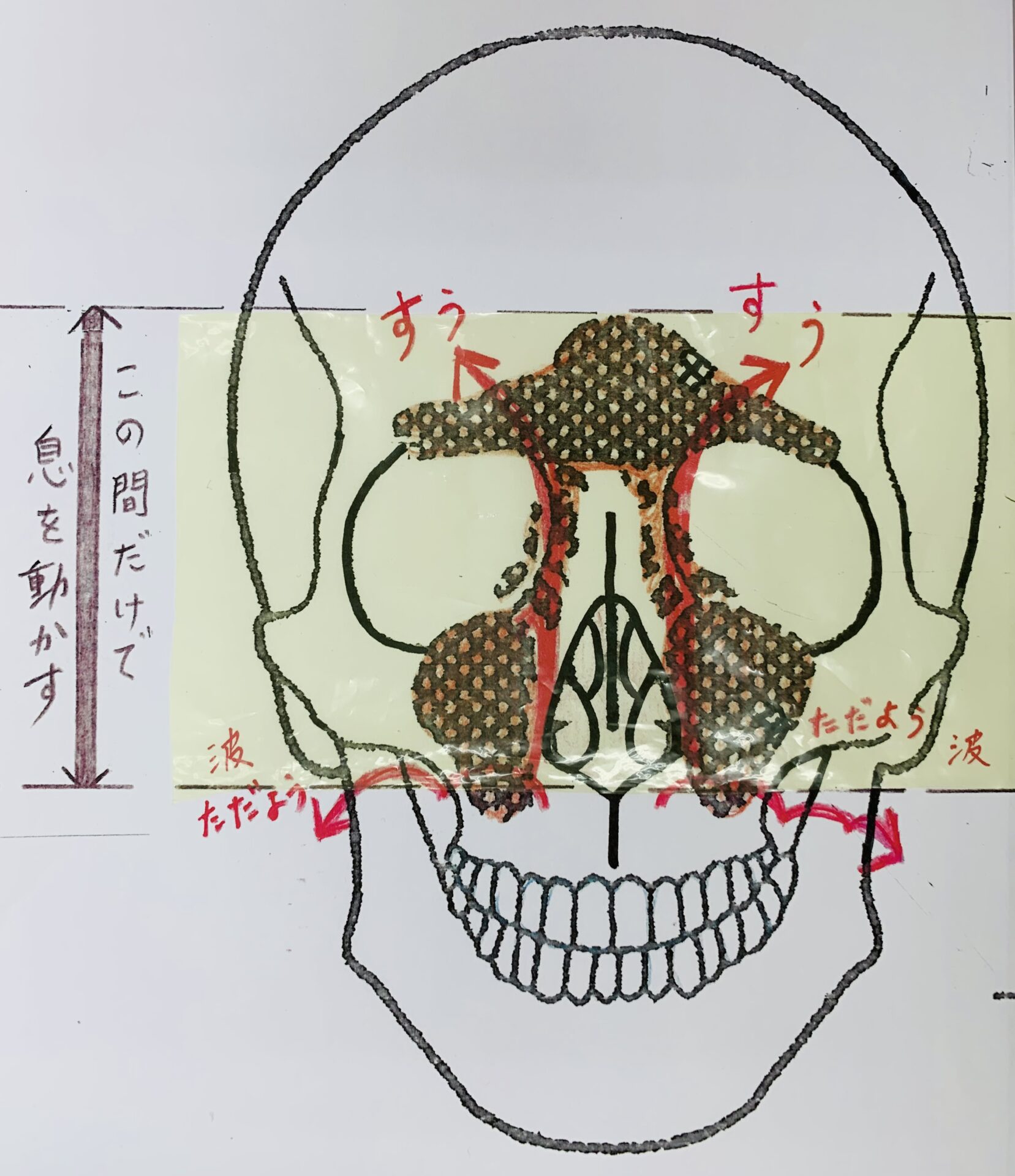息の通り道
まず、鼻呼吸で鼻腔・副鼻腔の内圧を高めます。次に、息を持続したり大きな声を出せるようにしましょう。
それには、顔の前面で上部にある息の通り道を確認します。⇒FAQ
舌で声の出る場所(鼻腔・副鼻腔)の息をふさいで息漏れを防ぐようにできましたか。
湖面(声を出す場所のイメージ)を作ったら、沈まない声を出すようにしましたね。
歌の字
(5)声を出す場所のイメージでは、声を息の湖面の上で弾ませるように、
(4)口蓋の上で声を出すでは、1階で子音を軽く、2階で母音を響かせました。
歌という漢字を見てください。口が2つあります。
歌
よくみると、人間の横顔のように見えませんか???
右側のつくりの部首は『あくび』ですが、のど(咽頭から喉頭)に見えないでしょうか?
『へん』の部分をみてください。
口蓋(口の中の天井)の下は1階の口腔、2階は、鼻腔・副鼻腔にみえますよね!
漢字は、古代中国からの表意文字ですが、すごいヒントを頂きました。
この漢字でみてゆくと、あくびの部分ですが、息(空気)の貯蔵庫になります。つまり、息(空気)はためておくだけで、動かさないでいただきたいのです。
息(空気)が動く息の通り道は、左上の『可』部分だけになります。
前から見ると、こんな感じです。手書きで失礼します。
息の通り道(図解)
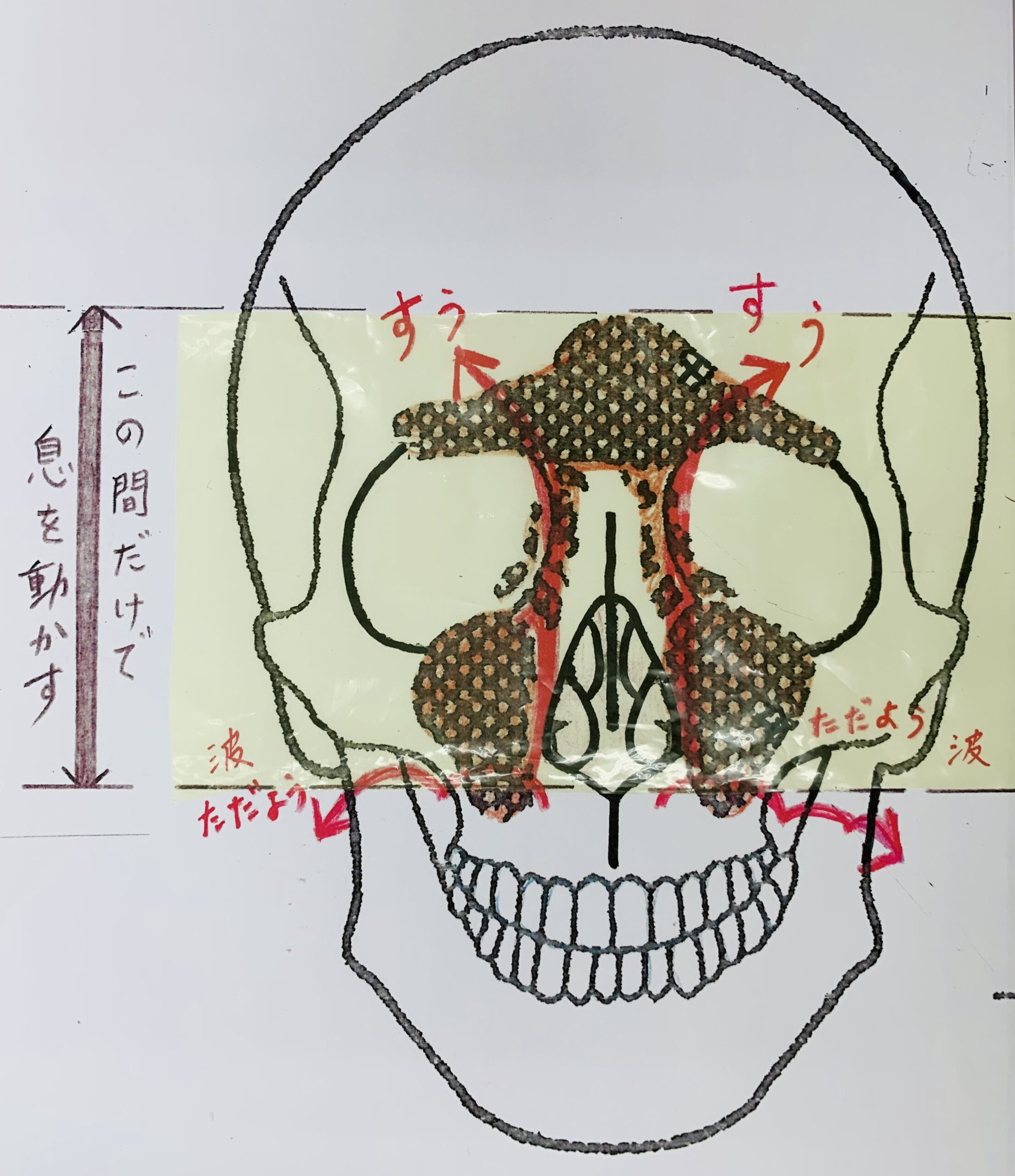
以前、声を出す場所を見つける練習をするとき、小さな声で短く出すようにしました。それは、鼻腔・副鼻腔あたりの息(空気)だけを使っていただくためでした。
「はっ」と声をだすと、息がこぼれ、声帯が閉じ、息は下がった状態になります。すぐに、息をもちあげて、一番はじめの発声時と同じ状態に戻らなければいけません。⇒(9)息の持ち上げ方、即!鼻呼吸にきりかえる法
このとき、息漏れを抑えるために、舌で口蓋をふさぐと効果的でした。⇒(5)声を出す場所のイメージ
※もしもできないときは、舌を外に出したまま、練習されてみるのもいいです。⇒嚥下障害と予防法
舌は下?
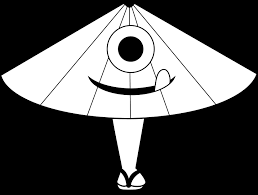
舌は、下と同音異義語になりますが、発声法では、舌は下にあってはいけません。
これから、舌は上にあるとお考え下さい。
例えば、一声発音すると舌は下に下がってしまうものです。気づいたら、いちいち上にあげなおしてみてください。
舌を口蓋の天井に張り付け、息漏れを防いだ状態が、息を止めている状態になります。
※一般的には、舌先は上歯の裏、舌根は下歯の裏にあります。
舌全体の力を抜くと、口の中の天井に、バキュームのように張り付けることができます。
息を吸うと同時に声を出してはいけない
ところで、息を吸うと同時に声をだし、息をはきながら話している人があるでしょう。
これは、息(声)が落ちた状態になっています。
息を吐き、息がたりないのに、話し続けたり、動き回ったりすると、
からだによくないです。⇒声で変わる健康
その状態を続けていると、
体がしびれたり、力が入ってこわばり、あちらこちらに凝りが生じてしまいます。
舌を利用して落ちた息を持ち上げる
息を鼻ですったら、その吸った分量だけの、おしゃべりや動作をしましょう。
そのとき、舌を口蓋の天井にバキュームのように張り付けて、息を持ち上げます。⇒嚥下障害と予防法 (9)息の持ち上げ方
息をたくさん吸う必要はありません。
が、吸うたびにお腹がひっぱられることを確認し、
吐く息のことは、特に考えなくてもいいと思います。⇒のどが疲れない音読法
声を出すことが、吐く息ですし、
声を出していなくても、息は勝手に漏れてなくなります。
うまくゆかない人は、舌先で上あごを持ち上げるようにしてみてください。左右別に挑戦し、副鼻腔の響きが作れる方から、練習してみましょう。舌は緩めるといいのですが、この場合、力を入れなければ、上あごは上がりませんね。すごい顔になりますよ。
レッスンでは、鉛筆を鼻の下ではさんで、息を持ち上げておりますよ。
息は横でなく縦に吸うこと
ここで、息の吸い方を確認します。
鼻から目のまわり、眉間やその上あたりまで、縦に吸うことを心がけてみてください。上図の矢印のようにされてください。
間違えても、口から吸って咽頭(のど)に息が激突!それで炎症をつくられたりされませんように、お気を付けください。⇒声の問題~よくある症例
(4)口蓋の上で声を出すでしたように、1階から2階へ、最短距離で上がれるように、
声の息の通り道を確保されてください。
それで息の湖面(5.声を出す場所のイメージ)を続けて設定してください。

ハンドソープのボディを「鼻腔・副鼻腔」に、
ポンプの口を「眉間とかまゆげ」に見立ててみてください。
ポンプから泡が出てくるように、声も鼻腔の高い所から、簡単に出てきます。
とはいっても、これは現代がマイクロフォンの声をつくる時代なので、
このたとえが適用できます。
本当のいい声は、完全に体から離れた所の空気が振動する感じです。
往年の歌手
師匠から、Francesco Tamagno の話を聞いています。
タマーニョの声は、スカラ座公演中、建物の外からでもその声が聞こえたそうです。
家のLPレコード(1903~1904年の録音)で Il Trovatoreを聞くと、
口跡(発音)が正確で、鼻腔・副鼻腔の口蓋の上で歌っていることが聞き取れます。
声の正体が、筋肉の振動か、それとも空気の振動か、すぐに判断できると思います。
太い息の柱
(2)鼻腔・副鼻腔に息をはらんで力抜くことでは、
頭のてっぺんから、臍下丹田につながる、太い孟宗竹を息の柱に見立るお話をしました。

太い息の柱
上図の歌の字のつくりの欠の部分に当たります。
発声時、のどの奥や、後頭部にあるような、空気(息)を使ってはいけません。
その部分の息は、満タンにして不動にしておいてください。
(上図の顔の前面上部を使う息の道とは別の息の通り道です。
鼻腔のそれより後ろ側の息の柱のことで、そこの息は動かさないでください。)
方言によって、感情の起伏によって、体調によって、
声は、あちこちの頭の骨から、反響して聞こえます。
声の散らばり
しかし、声をつくる決心をしたら、そのあちこちに散らばっている声は、
あきらめていただきたいと思います。
理由は、腹式呼吸の(1)声の出し方をするため、
そして、(2)鼻腔・副鼻腔に息をはらんで力を抜くためです。
では、今まで話してきた方言や自分らしい話し方を
あきらめなければいけないでしょうか。
そんなことはありません。
鼻腔・副鼻腔で声を出せるようになれば、
声を回して、声を自由自在にコントロールできるようになります。
声を出す場所はかわりますが、
方言も感情も、同じように表現できるようになるはずです。
何も心配はいらないのです。
さらに、今は短い声、小さい声の練習ばかりしていただいてますが、
そのうち、大きな声や、息を持続させる方法を覚えられます。
その勉強ため、太い息の柱は、重要なイメージとしておさえておいてください。
では次回は、(7)声の回し方について、書いてみようと思います。