口蓋の上で声を出す~発声法はまず発音から
今日は、口蓋の上で声を出すことを理解するために、発音についてお話します。正しい発声法は、正しい発音の上になりたつと、先生が言っておりました。
日本語の表記では、母音と子音とをわけて発音することは考えられません
ひらがなの「か」やカタカナの「カ」では、「KA」であることを考えません。
しかし、発声法では、「KA」を使い、「K」と「A」をわけて発音する練習をします。鼻腔・副鼻腔を響かせるのは、子音でなく、母音の方になります。⇒吃音の原因について
2階で~口蓋の上と下
口の中の天井を口蓋(口のフタ)といって、鼻腔と口腔をわけている場所があります。
そこを境に、1階2階とわけると、鼻腔・副鼻腔は2階ということになります。以後、便利のために、そう呼ばせてください。
口の開け方
口の開け方は発音にとって、かなり重要です。
母音は、『A、I、U、E、O』の5種類です。
口の開け方がきまると、声を出さなくても、「A、I、U、E、O」を伝えられます。
母音の発音は、発声法で『ヴォカリッザーレ』といって、万国共通。
鼻腔・副鼻腔の空気を使います。
実際はその上の頭から声が降りかかってくるように発声します。
基本となるのは、『A』「あっ」です。
(『あ』でなく『あっ』になる理由はあとでご説明します。)
はじめのうちは、『A』の口の形で、A、I、U、E、O全部発声します。
あらかじめ、歯医者にかかったときのような、大きな口をあけておいてください。
そのとき、上の歯茎の奥と下の歯茎の奥もみえることが理想です。
(口が開けられない人は、開ける練習から始めてみてください。)
(最終的には、口の奥の方だけ開いたらいいです。歯医者でするような口をあける必要はございません。はじめは奥歯が見えるように開けていただく方が進歩するかもしれません。)
子音の発音
子音は、アルファベットの母音以外です。歯、舌、くちびるを使って、口蓋の下(1階)で出します。
次に子音の『K』の発音です。
子音は、軽く発音することが肝心です。
『K』は、通常舌の根の両側あたりを緊張させて「くっ」と息だけでいいますが、
それでは口の中の息を動かすことになりますので、次のようにします。
上あごの前の方、上歯の裏あたりで、口を開けたまま『K』が発音できます。
この時、くれぐれも軽くやってみてください。
鼻の孔(あな)から息が軽くもれるようにしましょう。
そのあと間髪入れずに『A』「あっ」をやりますので、『KA』「かっ」になりますが、
『か』は『K』と『A』の合成作業であることを、覚えておいてください。
はじめは、顔が伸びたり縮んだりするようです。このときも、必ず鼻腔の圧力を感じてください。
「くっ」→「はっ」→「くっ」→「はっ」→同時に「かぁっ」という感じです。
1階→2階→1階→2階→同時に2階という感じですね。⇒(6)息の通り道
先人の技術(わざ)
むかし、歌舞伎の舞台稽古をTVでみていたときのことです。先代の羽左衛門が若手に教えていました。
「とんでもないこと!」の「と」はいわなくていい、「おんでもないこと!」といいなさい、といっていたのです。
これが2階の声でしょうか。
『TO』の子音のTをやりすぎないこと。さもないと舞台の遠くまで声が届かない、ということだったと思います。
また、これも随分昔になります。モンセラット・カバリエの「トスカ」の日本公演にいったとき。
横浜アリーナだったと思いますが、
『Vissi d’arte』のVが、iよりも前に、嵐の音のようにきこえてきました。
鼻腔にたっぷりと息をはらんでいるという証明。1階で発音するはずの『V』の上に感情があふれてきこえました。その後『i』がさらに迫ってきこえて、とても感動的でした。
声は2階から発せられると、ことばやその心を人にわからせ、感動をもたらします。⇒ミッション
母音は口蓋の上(2階)で発音
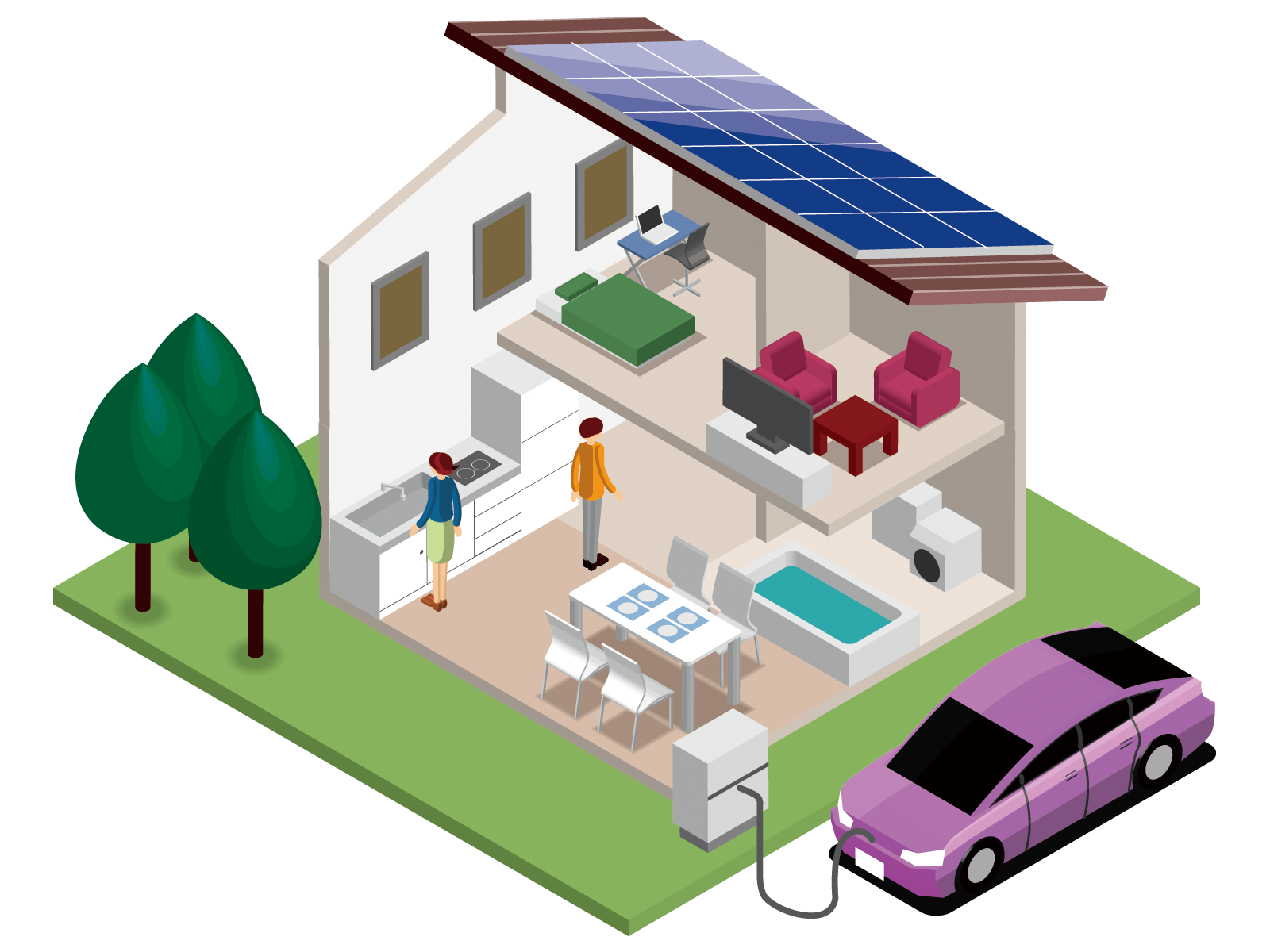
さて、ここでまとめてみましょう。
声は口蓋の上(2階)で出すものであること。
一時的に口蓋の下(1階)にもおりなければいけないこと。
口蓋の下(1階)の滞在時間をなるべく短く発音すること。
など、わかっていただけたでしょうか。
なぜ、口蓋の下(1階)で声を出す時間を短くするのか?⇒FAQ
それは、口蓋の下(1階)で声を出すと、声帯の筋肉を傷つけてしまうからです。声帯炎や声帯ポリープの原因にもなってしまうからです。
⇒声の問題~よくある症例
声帯炎や声帯ポリープの原因に
口蓋の下(1階)で『のど声』を出し続けると、歌手生命を縮めることになります。
口から息を吐く、吸う、口の奥に息が当たるのは、歌手にとって危険なことです。
声帯炎や声帯ポリープ、それから、上咽頭炎の原因になります。
咳、ぜんそく、痰切りなど、口蓋の下(1階)でする癖のある方も同じです。のど声のダメージと同じく、声帯炎等の病気になってしまうことがあります。
⇒声で変わる健康
出しにくい声を口蓋の下(1階)で無理に出すのはよしましょう。
声は出しやすい所から出ます。
若いうちから、口蓋の上(2階)で楽器のように声を出しましょう。
のどから離れた所に声や息の意識を持ってきましょう。
のどをいたわる習慣をつけていただきたいと思います。⇒のどが疲れない音読法
最後に、参考までに、芸能人の声帯ポリープ切除に関する記事をご覧ください。岡村隆史、正月休みに行った声帯ポリープ手術を語る
それでは次回、息の通り道について、お話しようと思います。
