口蓋の上で声を出す ~発音と発声法の関係~
1. 発音と発声の基本的な関係
疲れない発声法は、西洋式の発音の基礎の上に成り立ちます。 日本語では、ひらがなの「か」やカタカナの「カ」を発音するとき、「K」と「A」を分けて意識する習慣はありません。しかし、発声トレーニングでは子音と母音を明確に分けて発音する練習を行います。
特に鼻腔・副鼻腔を響かせるのは母音であり、この響きをコントロールすることが、響きの豊かな声を作る鍵となります。
2. 口蓋を「1階」と「2階」に分けて考える
口の中の天井部分を「口蓋(こうがい)」と呼びます。ここは鼻腔と口腔を隔てる構造であり、発声において重要な役割を担います。 便宜上、口蓋より上の鼻腔・副鼻腔を「2階」、口蓋より下の口腔部分を「1階」と呼びます。
- 母音は2階(口蓋の上)で響かせる
- 子音は1階(口蓋の下)で発音する
この位置関係を意識することで、声の響きと明瞭度が大きく向上します。
3. 口の開け方と母音の発声
母音は『A・I・U・E・O』の5種類ですが、口の開け方が定まれば、声を出さなくても母音の形を伝えられます。
発声法では「ヴォカリッザーレ」という国際的な母音発声法を用い、鼻腔・副鼻腔の空気を利用して、頭部の上から声が降りてくるような感覚で発声します。
最初は『A』の口の形を作り、その形のまま全ての母音を発声します。
練習初期は歯科治療時のように大きく口を開け、上・下の奥歯茎が見える程度を目安にします。最終的には、口の奥だけが開く自然な形に移行します。
4. 子音発声のポイント
子音(母音以外のアルファベット音)は、歯・舌・唇を使って1階で発音します。
例として『K』の発音では、舌根を強く緊張させず、上顎の前方、上歯の裏あたりで口を開けたまま軽く発音します。この際、鼻孔から軽く息が抜ける感覚を持つことが重要です。
その後すぐに『A』を発声して『KA』となります。これは「K」と「A」の合成動作であり、顔や表情筋の伸縮を伴いつつも、必ず鼻腔の内圧を感じながら行います。
5. 舞台芸術や声楽の事例
舞台芸術や声楽の現場でも、この「2階で響かせる声」の技術が活用されています。
例えば歌舞伎では、子音を強く出しすぎず、母音の響きで舞台奥まで声を届ける指導があります。
また世界的ソプラノ歌手モンセラット・カバリエの舞台では、子音の『V』さえも鼻腔に豊かに息をはらみ、母音と共に感情を乗せて聴衆に届かせていました。
6. なぜ1階での発声を短くすべきか
1階(口蓋の下)で長く声を出し続けると、声帯の筋肉に過度の負担がかかります。その結果、声帯炎や声帯ポリープ、上咽頭炎などの原因になることがあります。 特に「のど声」や、咳・喘息・痰切りを口蓋の下で行う癖がある場合は注意が必要です。
7. 健康な発声のための習慣
- 声は可能な限り2階(口蓋の上)で響かせる
- 1階(口蓋の下)での発声は必要最小限にとどめる
- 若いうちから「のどから離れた位置」で声を響かせる習慣をつける
これにより、のどの負担を軽減し、声の持続性や表現力が向上します。
まとめ
口蓋を意識した発声法は、声の響き・明瞭度・健康維持に直結します。
母音は2階(鼻腔・副鼻腔)で響かせ、子音は1階で軽く発音する。このバランスを守ることで、舞台・歌唱・日常会話すべてにおいて、無理なく心地よい声を届けることができます。
⇒吃音の原因について
⇒(6)息の通り道
⇒ミッション
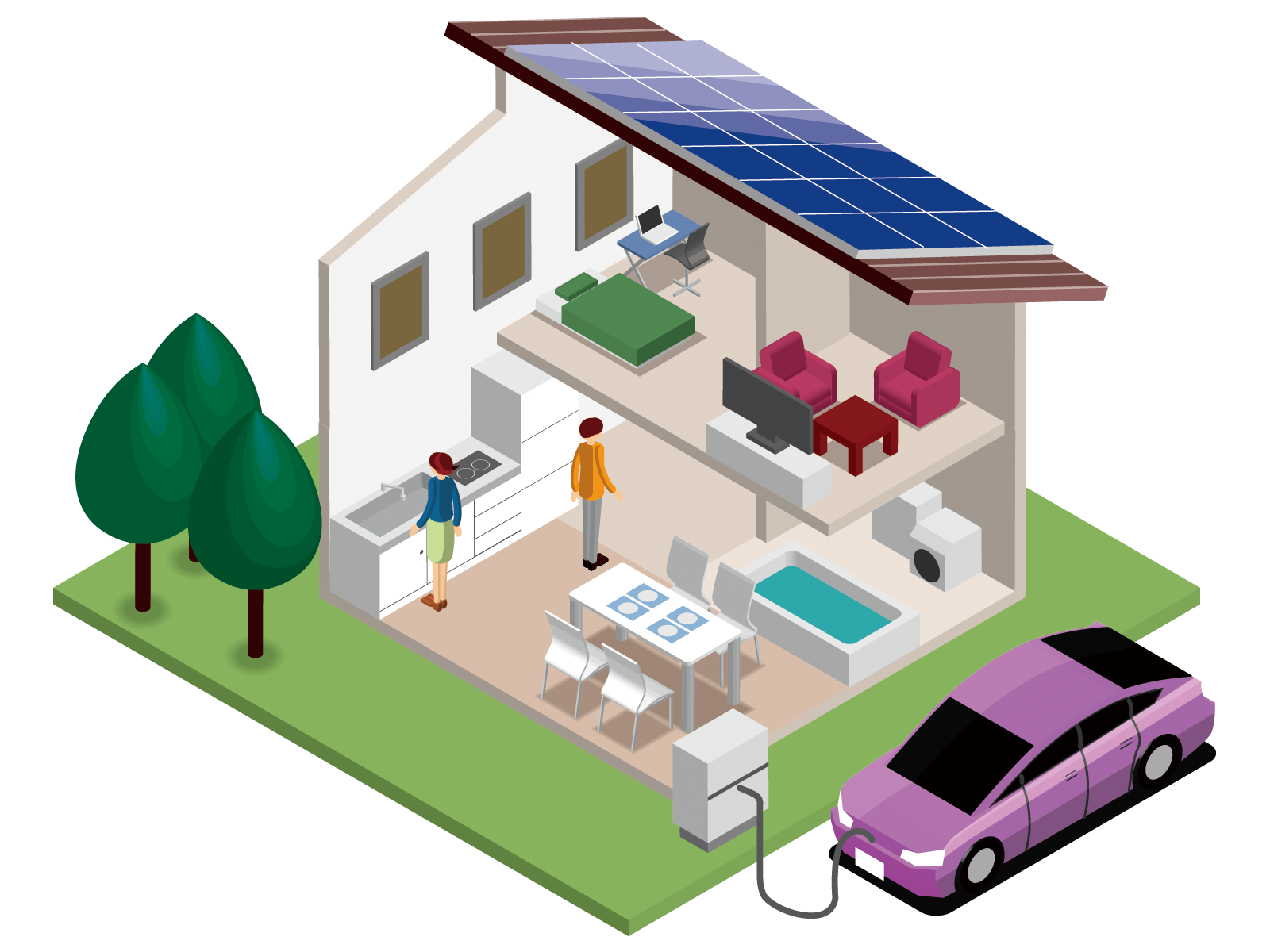
⇒FAQ
⇒声の問題~よくある症例
⇒声で変わる健康
⇒のどが疲れない音読法
又参考までに、岡村隆史、正月休みに行った声帯ポリープ手術を語る をごらんください。
