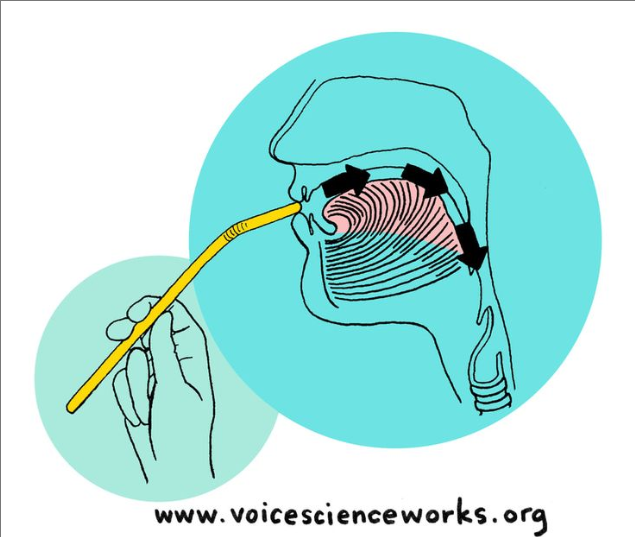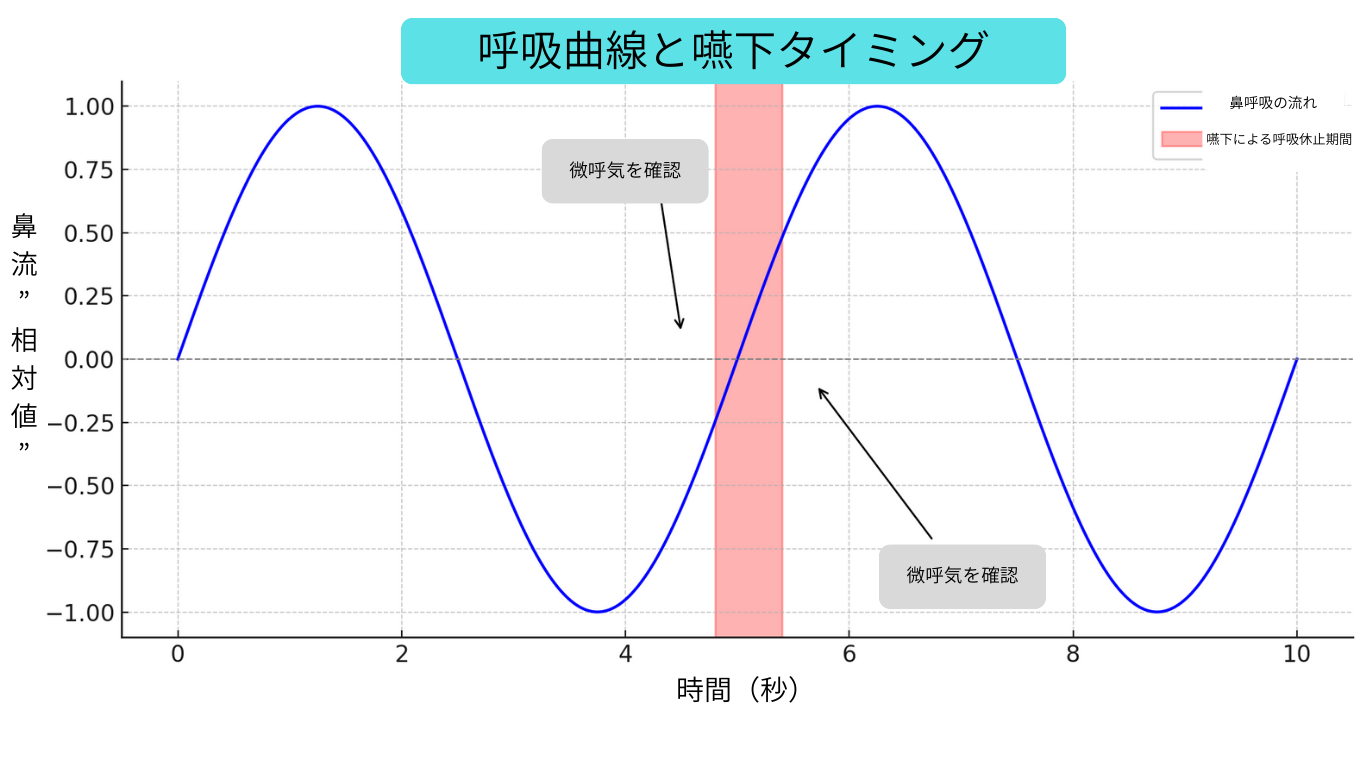【ストロー発声は声帯を守る応急処置】
Q. 耳鼻咽喉科で、吃音の方や誤嚥のある方に「ストロー発声」といって、コップの水にストローを差し、ぶくぶく音を出す練習をさせています。
この方法は確かに効果があるようですが、息を吐くことになり口呼吸になります。また腹式呼吸の訓練にもなると言われますが、発声法トレーナーの私には腑に落ちません。ストロー発声法はどんなからくりなのか、本当に良い方法なのですか?ちょっとAIに聞いてみました。
A. はい、ストロー発声には一定の根拠がありますが、同時に限界やリスクもあります。順に整理しましょう。
1. ストロー発声のしくみ
ストロー発声は音声リハビリやボイストレーニングで SOVT(半閉鎖声道法:Semi-Occluded Vocal Tract)と呼ばれる技法のひとつです。
・ストローで息の出口を細くすると、喉の奥に「背圧(back pressure)」がかかります。
・この圧が声帯の動きを安定させ、振動が整い、のどの負担を減らします。
・水に差し込んでぶくぶくすると、水圧と気泡の抵抗がさらに呼気を安定させます。
![]() 声帯を守るための“補助器具”のような役割なのです。
声帯を守るための“補助器具”のような役割なのです。
2. 効果がある理由
・吃音の方 → 呼気が一定化し、声帯の過緊張がやわらぐ
・嚥下障害の方→ 呼気を長く保つ練習になり、呼吸と嚥下の協調にプラス
・声のリハビリ→ 声帯の押しすぎや摩耗を防ぐ
👉短期的にはとても有効とされています。
3. 問題点・リスク
一方で、やり方を誤ると問題があります。
・息を強く吐きすぎると → 単なる口呼吸の訓練になる
・水にぶくぶく → 誤嚥のある方にはリスクになる場合がある
・長期的に続けると → 「鼻呼吸を基本にした発声」から離れてしまう可能性がある
![]() つまり、声帯保護には役立ちますが、「呼吸法教育」にはならないのです。
つまり、声帯保護には役立ちますが、「呼吸法教育」にはならないのです。
4. 腑に落ちない理由
質問者が「腑に落ちない」と感じられるのは正しい直感です。
ストロー発声は 「腹式呼吸+口呼吸の形」に近いので、「鼻呼吸と舌による呼気制御」という本来の原則とは矛盾してしまいます。
5. 結論
・ストロー発声法は短期的なリハビリ・練習としては有効
・ただし本質的な呼吸法教育にはならない
・位置づけとしては「声帯のリハビリ用ツール」であり、「根本的な健康発声法」とは別物
![]() 「応急処置としては役に立つ。でも最終的には鼻呼吸と舌による発声呼吸に戻していくべき」というのが正確な整理です。
「応急処置としては役に立つ。でも最終的には鼻呼吸と舌による発声呼吸に戻していくべき」というのが正確な整理です。
※まとめ※
ストロー発声は「声帯を休ませる補助法」。
本当の呼吸と声の健康は、舌が上にあり、鼻呼吸で息を止めずに続けられることにあります。
関連記事
第2回 「吐いて!」の落とし穴 —— ヨガ・筋トレスクワット・ストレッチの呼吸を考え直すhttps://spiratanto.com/training-yoga-nasal-breathing-safety/